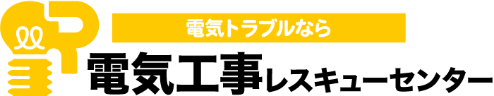「ピリッ」と指先に走る不快な感覚、突然家中の電気が消えてしまう停電、理由もなく急に跳ね上がった電気代。それは単なる偶然ではなく、「漏電」という見過ごせないトラブルの兆候かもしれません。
この記事では、今まさにその不安に直面している皆さまに向けて、漏電の正しい知識といますぐ取るべき安全な行動、そして安心して相談できる専門家を見つけるためのポイントを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、漏電の疑問は解消され、具体的な解決策への一歩を踏み出せるはずです。どうぞ、落ち着いて読み進めてください。
漏電トラブルでお困りですか?電気工事レスキューセンターなら、地元をよく知るプロが迅速に対応します。24時間365日、お客様の安全を守ります。無料相談をご利用ください。
この記事で分かることの要約
漏電したらどうなる?症状をチェック

漏電とは、電気が本来通るべき道筋から外れてしまう現象を指します。
私たちの家に届けられる電気の通り道は「絶縁体」と呼ばれる電気を通しにくい素材で覆われており、電気が外に漏れ出ないように守られています。
しかし、何らかの理由でこの絶縁体が損傷したり、劣化したりすると電気が本来の道から外れて、地面や建物の金属部分、さらには人間の体へと流れ出してしまうことがあります。これが漏電です。
漏電が発生していると以下症状が発生します。
漏電ブレーカーが頻繁に作動する
漏電ブレーカーは、電気が通る「行き」と「帰り」の電流の量を常に監視しています。
正常な状態であれば、行きと帰りの電流はまったく同じ量になります。しかし、漏電が発生すると、電気が途中のどこかで外に逃げてしまうため、行きと帰りの電流のバランスが崩れ、差が生じます。
このわずかな電流の差を検知すると、漏電ブレーカーはわずか0.1秒以内という速さで電気回路を遮断します。そのようにして、感電や火災といった重大な事故を未然に防いでくれます。
つまり、漏電ブレーカーが頻繁に作動するということは、ご自宅のどこかで電気が漏れている可能性があるというサインなのです。
電気代の高騰
漏電ブレーカーが落ちない程度の小さな漏電でも決して安心はできません。電気が無駄に流れ続けている状態ですから、当然その分の電気代が加算されてしまいます。
ご家庭の電気使用状況は変わっていないのに、電気代が急に数千円から1万円ほど高くなった場合は、漏電が原因である可能性が十分に考えられます。
家電製品の故障
漏電は電化製品そのものにもダメージを与えます。規定外の電流が流れることで内部の回路に負担がかかり、家電の寿命を縮めたり故障の原因となったりします。
結果的に、無駄な電気代と高価な家電の買い替え費用という二重の経済的損失を招くことになります。
焦げ臭い匂いや異音は危険のサイン
電気設備や家電製品から焦げたようなプラスチックが焼ける匂いがしたり、配線の奥から「バチバチ」と火花が散るような音が聞こえたりしたことはありませんか?
これらは漏電が進行し、電気配線や機器が過熱している非常に危険な兆候です。
電気が本来通らないはずの場所にわずかに流れ続けることで、ヒーターのように発熱する「抵抗加熱」という現象が起きている可能性があります。この熱が、近くにあるホコリや紙くずなどの可燃物に引火すると、あっという間に火災に発展してしまいます。
異変に気づいたら、気のせいかなと放置せず、すぐに使用を中止して専門家にご相談ください。
照明がチカチカ点滅する不調
照明が点滅したり、明るさが不自然に変動したりすることも、漏電の兆候の一つかもしれません。漏電によって回路内の電流が不安定になり、照明などの電力供給が一時的に乱れることが原因として考えられます。
特に、特定の部屋や照明だけがチカチカする場合は、その回路や照明器具自体に問題が発生している可能性が高いです。また、特定の家電製品が突然動かなくなったり、何度も電源が切れたりする場合も、漏電による故障や回路への負担が疑われます。
雨の日に限って停電する
雨漏りなどで雨水が電気配線にかかり、漏電を引き起こしている可能性があります。
水回りにある家電の調子が悪い
キッチンや洗面所など湿気の多い場所で使用する家電は、絶縁体の劣化が早まりやすい傾向にあります。
屋外照明が頻繁に消える
玄関先や庭の屋外照明は雨風にさらされるため、防水機能の劣化によって漏電が起きることが考えられます。
漏電かも?と気づいたときの初期対応

漏電しているかもしれないと感じたとき、焦らずに以下の3つのステップで状況を確認し、安全を確保しましょう。
- ブレーカーの状態を落ち着いて確認する
- 漏電している箇所を特定する
- すぐにプロへ相談する
この手順は、ご自身で原因箇所を特定するための有効な方法ですが、あくまで安全な範囲で行うことが大前提です。
1:ブレーカーの状態を落ち着いて確認する
まずは、分電盤(ブレーカーボックス)の位置を確認し、どのブレーカーが落ちているか確認してみましょう。
分電盤には通常、3つの主要なブレーカーが設置されています。もし、家全体の電気が消えていて、中央にある「漏電ブレーカー」だけが「切」になっていたら、漏電が発生している可能性が高いと判断できます。
2:漏電している箇所を特定する
漏電している箇所を特定する手順は非常にシンプルです。以下の手順通りに確認しましょう。
- すべてのブレーカーを「切」にする
- 漏電ブレーカーを「入」にする
- 安全ブレーカーを一つずつ「入」にする
各部屋に対応する安全ブレーカーを、一つずつゆっくりと上げていきます。
このとき、あるブレーカーを「入」にした途端、再び漏電ブレーカーが「切」になったら、その時に上げたブレーカーに対応する回路で漏電が起きていると判断できます。
原因が特定できたら、該当の安全ブレーカーは「切」のままにしておけば、他の部屋の電気は通常通り使えるようになります。
3:無理せずすぐにプロへ相談する
特定作業で原因がわからなかったり、不安を感じたりした場合は決して無理をしてはいけません。電気は目に見えない危険であり、ご自身で壁の中の配線を修理したり、安易に触れたりすることは、感電や火災といった重大な事故につながる恐れがあります。
漏電の調査や修理は、国家資格である「電気工事士」の資格を持つ専門家でなければ行うことができません。
また、ブレーカーが頻繁に落ちる原因が漏電なのか、単なる使いすぎ(過電流)なのか、それともブレーカー自体の故障なのかを正確に判断することも素人には困難です。
電力会社は、ブレーカーの交換や修理といった設備に関する対応は原則行わないため、漏電の専門家である電気工事会社に相談することが安全で確実な方法です。
漏電の放置が招く見過ごせない危険

漏電のサインに気づきながら「まあ大丈夫だろう」と放置してしまうと、非常に重大なリスクを招くことになります。
これらの危険性は、決して他人事ではありません。漏電によるリスクについて詳しく解説します。
感電による人身事故
漏電が発生している電化製品や金属部分に人が触れると、体に電気が流れて感電事故につながります。感電は以下のように流れる電流の量によって人体に与える影響が大きく変わってきます。
- 1mA:指先に「ピリッ」と感じる程度の痛み
- 5mA:強い痛みを感じ、体がしびれる
- 20mA:筋肉が収縮し、呼吸困難に陥る
- 50mA以上:わずかな時間で命を落とす危険性がある
15mAから30mA程度の漏電でも漏電ブレーカーが作動する仕組みになっていますが、感電は命にかかわる重大な危険です。スマートフォンを充電しているケーブルからの感電事故など、身近な場所でも起こりうることを認識しておくことが重要です。
重大な漏電火災
漏電は火災の原因としても危険です。漏電によって火災が起きる主なメカニズムは以下の2つがあります。
- 発生する火花(スパーク)が近くにある可燃物やガスに引火するケース
- 電気が流れるべきではない部分に微弱な電流が流れ続けることでヒーターのように発熱し出火に至るケース
特に注意が必要なのが、日常生活に潜む「トラッキング現象」です。トラッキング現象とは、コンセントにプラグを差し込んだまま放置していると、間に溜まったホコリが空気中の湿気を吸い込み、電流の通り道(トラックと呼ばれます)を形成してショートし、発火に至る現象です。
この現象は、冷蔵庫やテレビの裏側、水槽や加湿器のそばなど普段あまり掃除をしない場所や湿気が多い場所で特に起こりやすいです。
トラッキング現象による火災は、壁の内部など見えない場所で発生することが多く、発見が遅れがちです。日頃から以下の対策を実践することで、リスクを大きく減らすことができます。
- 定期的な掃除
- プラグの抜き差し
- コンセントキャップの使用
高額請求トラブルを避ける!安心できる電気修理業者選びのポイント

「いざ業者に頼むとなると、高額な費用を請求されないか不安」といった懸念を抱くかもしれません。
ここでは、安心して任せられる業者を見つけるための以下の3つのチェックポイントをお伝えします。
- 電気工事士の資格や実績を確認する
- 明確な見積もりを提示してくれるか
- 保証やアフターサービスは充実しているか
電気工事士の資格や実績を確認する
漏電修理は感電のリスクを伴う危険な作業であり、法律に基づき「電気工事士」の国家資格が必要です。この資格を持たない業者が工事を行うことは違法であり、信頼できません。
業者に相談する際には、必ず資格保有者が在籍しているかを確認しましょう。
さらに、会社の設立年数や実績、そしてインターネット上の口コミや評判も重要な判断材料となります。拠点や電話番号が実在しない業者は悪質である可能性もあるため、注意が必要です。
明確な見積もりを提示してくれるか
不当な高額請求を避けるためには、見積もりの内容をしっかり確認することが不可欠です。以下の点に注意しましょう。
- 「一式〇〇円」のような曖昧な表記の業者には注意する
- 調査費用と修理費用が明確に分かれているかを確認する
適正な料金で納得のいくサービスを受けるためには、複数の業者から「相見積もり」を取って比較検討することをおすすめします。相見積もりをすることで工事内容の妥当性や費用相場が明確になり、より良い業者を選べる可能性が高まります。
また、相場と比べてあまりにも安すぎる、または高すぎる業者にも注意が必要です。
保証やアフターサービスは充実しているか
工事が終わればすべてが解決というわけではありません。万が一、工事後に不具合が発生した場合に備え、一定期間の保証やアフターサービスが充実している業者を選ぶと安心です。
以下の保証やアフターサービスの有無を確認しましょう。
- 工事後の不具合やトラブルに対する補償
- 施工中に建物に損害を与えた場合の補償
良心的な業者であっても人が作業する以上、リスクはゼロではありません。万が一の事態にも迅速に対応してくれる責任の所在を明確にしている業者を選ぶことで長期的な安心を得ることができます。
漏電修理の費用相場

漏電修理の費用は、原因や作業内容によって大きく変動します。ここでは、一般的な費用相場を内訳ごとに具体的に解説しますので、業者から提示された見積もりが妥当かどうかを判断する際の参考にしてください。
漏電の原因調査費用
多くの電気工事会社では、修理工事とは別に「原因調査費用」が発生します。これは、漏電箇所を正確に特定するための専門的な作業にかかる費用です。
漏電の原因調査費用の相場は約1.3万円〜1.9万円です。具体的には以下の2つの内訳に分けられます。
基本調査費
電気工事業者が自宅を訪問して以下を行い、漏電の原因を特定するための費用です。
- 分電盤の電圧・絶縁測定
- 各回路の絶縁抵抗測定
- コンセントや配線の損傷の目視点検
専門業者の中には、この調査費用が比較的安価に設定されている場合もあります。
応急処置費
調査の結果、すぐに修理ができない場合や部品の取り寄せが必要な場合に、一時的に電気が使えるようにするための応急処置にかかる費用です。根本的な解決ではないため、あくまで一時しのぎの対応となります。
漏電の修理・改修工事費用
原因が特定された後の修理・改修工事にかかる費用相場は、以下の通りです。
| 作業内容 | 費用相場 | 費用が変動する要因 |
|---|---|---|
| ブレーカーの交換・修理 | 約20,000円~24,000円 | ブレーカーの種類、性能、メーカーなど |
| 分電盤の交換・修理 | 約30,000円~45,000円 | ご家庭の回路数、分電盤の機能、サイズなど |
| コンセント・スイッチの交換 | 約4,000円~9,000円 | 複数箇所を交換するか、防水機能など特殊な機能の有無など |
| 配線の部分的な引き直し・修理 | 約20,000円~ | 作業場所(壁の中など)、建物の構造(鉄筋コンクリート造など)など |
この費用は、作業場所や建物の構造(鉄筋コンクリート造など)によって高くなる傾向があります。必ず事前に見積もりを取り、実際の費用を確認してください。
漏電を未然に防ぐ!家庭でできる予防策

漏電は、いつ、どこで起きるかわからないからこそ、日頃からの予防が何よりも大切です。
少しの意識と行動で、ご家庭の電気の安全を大きく高めることができます。家庭でできる予防策について詳しく解説します。
コンセント周りのこまめな清掃
漏電火災の原因で特に多いのが、コンセントとプラグの間に溜まったホコリが原因で起こる「トラッキング現象」です。この現象は、プラグを長期間差しっぱなしにしている場所で、ホコリが湿気を吸い込み、電気が通る道を作り出すことで発生します。
これを防ぐためには、冷蔵庫やテレビの裏など、普段目の届かない場所にあるプラグを時々抜いて、乾いた布でホコリを丁寧に拭き取る習慣をつけましょう。
使っていないコンセントには専用のキャップを取り付けるのも非常に効果的です。
電気コードの正しい使い方と管理
電気コードの扱い方一つでも、漏電のリスクは大きく変わります。コードを家具で挟んだり、きつく束ねたり、踏んだりすると内部の配線が損傷し、断線や漏電の原因となります。
また、一つのコンセントに複数のプラグを接続する「たこ足配線」も、許容量以上の電流が流れ、コードやコンセントが過熱して火災につながる危険性があります。
使用する機器の消費電力を確認し、無理のない配線を心がけましょう。
古い電化製品や電気設備は定期的な点検を!
長年使い続けている電化製品は、内部の絶縁体が劣化している可能性が高く、頻繁に漏電を起こすようであれば買い替えを検討することが安全への近道です。
また、築年数の古い建物では、壁の中の見えない配線が老朽化していることも考えられます。感電や火災といった重大な事故を未然に防ぐためにも、電気工事の専門家に定期的な点検を依頼することをおすすめします。
まとめ
漏電は、感電や火災、経済的損失につながる見過ごせないトラブルです。しかし、正しい知識と落ち着いた行動、そして信頼できる専門家の助けがあれば必ず解決できます。
漏電の兆候には、ブレーカーが落ちるだけでなく、異音や異臭、電気代の高騰、家電の故障など様々なものがあります。まずはブレーカーを確認し、安全な範囲で原因箇所を特定する初期対応が重要です。
自力での修理は危険なため、国家資格を持つ専門業者に任せるべきです。安心できる業者を選ぶには、資格、明確な見積もり、保証・アフターサービスの3つのポイントが鍵となります。
もしご自宅で少しでも「もしかして」と感じることがあれば、一人で抱え込まず電気工事レスキューセンターにご相談ください。電話、メール、LINEでのお問い合わせをお待ちしております。
よくある質問
漏電ブレーカーが頻繁に落ちるのですが、故障でしょうか?
漏電ブレーカーが頻繁に落ちる場合、漏電している可能性が高いです。しかし、ブレーカー自体の経年劣化や故障が原因で、漏電していなくても作動してしまう「不要動作」の可能性も考えられます。どちらにせよ、放置すると危険なため、専門の電気工事業者にご相談ください。
漏電調査や修理に「アース線」は関係ありますか?
関係があります。アース線は、漏電した電気を安全に地面に逃がすための重要な役割を担っています。特に、洗濯機や冷蔵庫など水回りの家電には必ず設置すべきものです。
アース線が正しく接続されていないと、漏電が発生しても漏電ブレーカーが作動しないことがあるため注意が必要です。
賃貸住宅でも勝手に業者を呼んでもいいですか?
漏電は緊急性が高いトラブルですが、賃貸物件の場合は、まず管理会社や大家さんに連絡することが第一です。
自己判断で修理業者に依頼してしまうと、後で修理費用を巡ってトラブルになる可能性があります。まずは状況を正確に伝え、指示を仰ぎましょう。